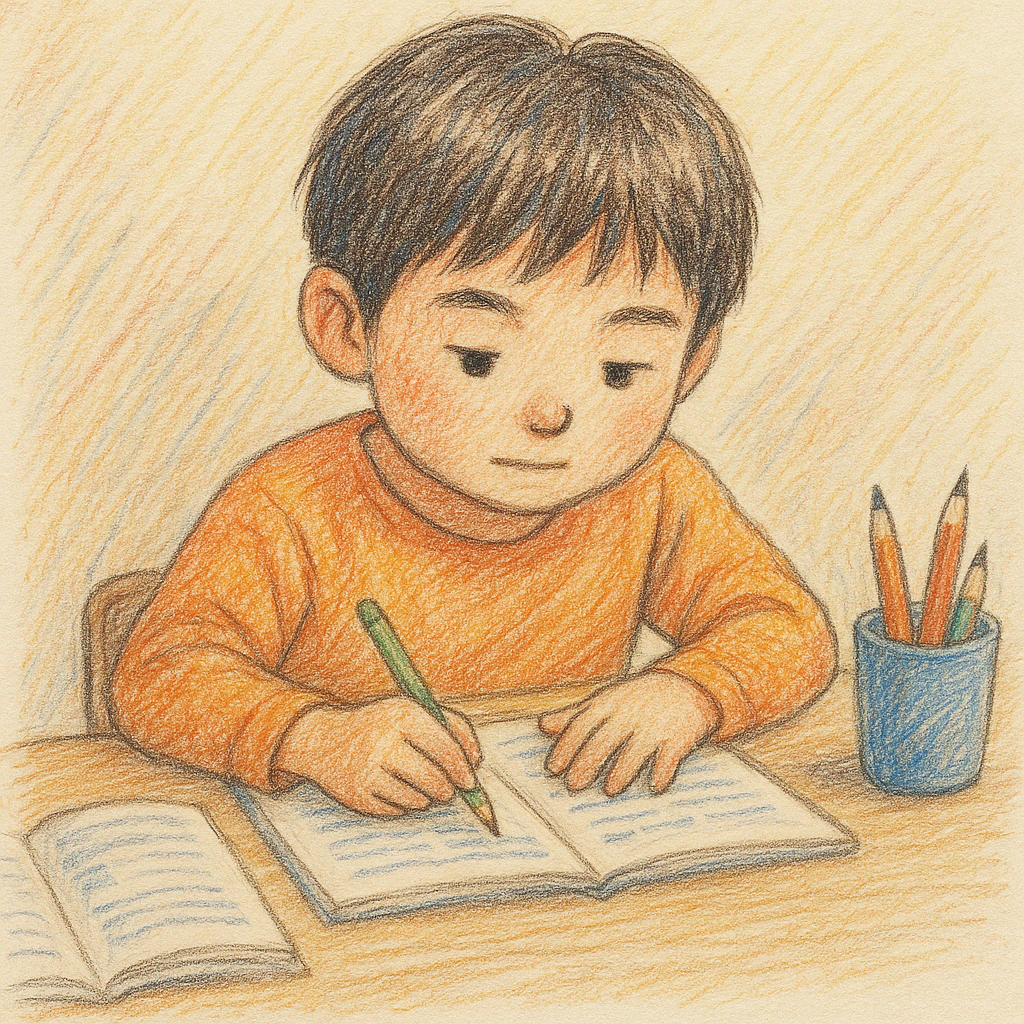こんにちは。学習支援サイト「TSUMIKI」へようこそ。
この記事では、「うちの子、なんだか勉強が苦手みたい…」「もしかして学習障害かも?」と思ったときに、家庭で気をつけて見てほしいチェックポイントを5つご紹介します。
「学習障害(LD)」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、まず大切なのは、「その子の得意・不得意を知って、力を伸ばしていくこと」です。この記事を読めば、お子さんの困りごとに気づくヒントが得られるはずです。
学習障害とは?かんたんに説明すると…
学習障害(LD)は、知的な発達には問題がないのに、「読み」「書き」「計算」など、特定の分野だけがとても苦手になる状態のことです。たとえば、話すのは得意なのに、文字を読むのがすごく苦手…というようなケースがあります。
これは、「やる気がない」とか「勉強がきらい」ではありません。脳のはたらき方が少しだけちがうだけなんです。
家庭で気づけるチェックポイント5選
✅ 1. 音読や読み聞かせが苦手
お子さんに音読をさせたとき、こんなことはありませんか?
- 文字をひとつずつ読むのに時間がかかる
- 行をとばしたり、同じ行を何度も読んだりする
- 「う」「ぬ」や「わ」「ね」など似た文字をよく間違える
これは、「読み」に関わる学習障害(ディスレクシア)のサインかもしれません。
とくに「書いてある言葉の形」と「意味」がうまく結びつかない子は、読みを覚えるのに時間がかかります。
✅ 2. ひらがなや漢字の書き間違いが多い
たとえば…
- 「さ」と「ち」、「め」と「ぬ」をよく間違える
- 漢字を覚えるのにすごく時間がかかる
- 文字を逆さに書いてしまう(例:「し」を「j」のように書く)
これは、「書く」ことが苦手な子によく見られる特徴です。
何度練習しても覚えられないと、本人もイライラしたり自信をなくしたりします。
✅ 3. 計算はできるのに文章問題になると手が止まる
「2+3=5」はすぐにできるのに、「りんごが2こ、みかんが3こあります。ぜんぶでいくつ?」となると考え込んでしまう…。
これは、文章を読んで意味を理解し、必要な情報を取り出すという力が必要だからです。
学習障害のある子は、「読む」「聞く」「理解する」のどこかでつまずいていることがあります。
✅ 4. 曜日や順番をなかなか覚えられない
「月・火・水・木…」と、順番に並んだものを覚えるのが苦手な子がいます。
- 月曜日の次が思い出せない
- アルファベットや九九の順番がごちゃごちゃになる
これは、ワーキングメモリ(短期記憶)の使い方がちょっと違う子に多い特徴です。
言葉で聞いたことを一時的に覚えておく力が弱いと、順番やルールを覚えるのが大変になります。
✅ 5. すぐに集中が切れてしまう、でも夢中になると止まらない
学習障害のある子は、注意力や集中力にムラがあることがあります。
- 宿題に取りかかるまでに時間がかかる
- 忘れ物やなくし物が多い
- 興味があることにはびっくりするくらい集中する
これは、注意欠如・多動症(ADHD)の特徴と重なることもあります。学習障害とADHDは一緒に見られることも多く、「ただの性格」と思われてしまいがちです。
「気になる」=「すぐに病院へ行く」ではない
ここまで読んで、「うちの子、いくつか当てはまるかも…」と心配になった方もいるかもしれません。でも、1つでも当てはまったら学習障害というわけではありません。
子どもたちはそれぞれ違うスピードで成長しますし、苦手なことがあっても、環境や声かけ次第でぐっと変わることもあります。
おうちでできる、やさしいサポートのコツ
- 間違いを責めず、「チャレンジしたこと」をほめる
- 「できた!」を増やすために、ステップを小さくする
- 書くのが苦手なら、話す・動かすなど別の方法も試す
- 困っていることを学校の先生にも相談してみる
そして、「あなたはあなたのままで大丈夫」というメッセージを、何よりも伝えてあげてください。自分を認められる力が、子どもをぐっと伸ばします。
まとめ:気づくことが、やさしい支援の第一歩
「もしかして学習障害?」と思ったとき、大事なのは「早く見つけて、正しく理解すること」です。
あなたのお子さんが困っているときに「気づいてくれる大人」がそばにいること。それだけで、子どもは安心し、自信を取り戻していきます。
気になることがあれば、発達支援センターや学校の先生、専門の相談窓口に話してみましょう。
「ひとりで悩まないこと」が、支援の第一歩です。
📌 TSUMIKIでは、学習障害のある子どもたちの「できた!」を応援しています。
次回の記事では、「学習障害の子どもに合った勉強法」について詳しくご紹介します。
ぜひまたチェックしてみてくださいね!